キニウムの部屋>フランス音楽の扉>作曲家のページ>
| サン=サーンス(カミーユ)Saint-Saëns,Camille(1835〜1921) |
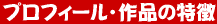
一言で言うなら「職人」的に大変多彩な作品を残した作曲家です。確か「リンゴに実がなるよう」に作曲したとも言われています。彼は小さいときよりピアニストとして才能をあらわし、パリ音楽院でオルガンと作曲を学びました。ベートーヴェンに傾倒し、ワーグナーの影響を受けつつも、フランス音楽の優位を確立するために1871年に国民音楽協会を作った人です。
作風は至って保守的でロマンティック、古典主義的な音楽です。安心して聞ける作曲家でしょうか。ただ他の作曲家に比べると魅力という点では「おもしろくない」作曲家です。個性がないのが個性です。こういう人がユーモアを持って曲を作ると職人の技が冴えたりするから面白いですよね。「動物の謝肉祭」などはその典型です。はったりをかますのも「うまい」ですよ。「オルガン」なんかでは筋書き通りハデにぶちかましてくれますが、意外性はないですね。お約束通りの音楽です。 たぶん映画音楽なんか書かせたら一流だったかも知れません。
ちょっと厳しい批評ですが、どれも同じに聞こえてしまうのは私が聞き込んでいないのが原因かな〜。どの曲もそこそこ書けているのですがそれ以上は……。
マイナーな曲では結構ファンは多い気がしますがね。

やっぱり組曲「動物の謝肉祭」でしょうね、聞き始めるなら。というよりクラシックの入門曲としても、ほんと良くできてます。いろいろな動物が次々登場する「動物園」みたいな曲です。クラシックになじみのない人とドライブをするときにかけてあげましょう。そんなわかりやすい名曲です。 単独では「白鳥」が有名ですが、(ほんとこの間のお葬式でもかかっていたのには参った!)他の曲もなかなか動物の生態をよくあらわしていて秀逸。職人の技が冴えまくっています。個人的には「水族館」が好きですが、天国の地獄のパロディーがゆっくりのテンポで登場したり「象」、音階の練習をしている「ピアニスト」が登場したりと、ユーモアのセンスが抜群の組曲です。最後は今まで出てきた動物が旋律で全部登場してどんちゃん騒ぎで終わります。いやー気分爽快楽しかった!……こういう曲って時々聞くとほっとしますよね。 この曲生前は出版を許可されなかったそうです。こんなふざけた曲を出版するなんて、彼のプライドが許さなかったと見えます。
あと有名なのは交響詩「死の舞踏」ですね。骸骨がヴァイオリンを持って踊っている、そういう曲です。
交響曲では第3番「オルガン付き」は最後オルガンの大音響でオーディオマニアにも受けの良い名曲です。作風としてはドイツ・オーストリア寄りの雰囲気ですから、そちら方面から鑑賞の手を伸ばしている人は取っつきやすいでしょう。フランス風ベートーヴェン?みたいな曲。フィナーレはなかなかハデでストレス解消にはいいかも。
序奏とロンド・カプリチオーソはヴァイオリンの独奏がなかなかメランコリックで泣かせます。
歌劇「サムソンとデリラ」のバッカナールは吹奏楽でも演奏されます。
よく考えてみたら結構CMで使われている曲が多いですねぇ。
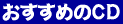
さて動物の謝肉祭はいろんなCDがでています。私のお薦めはジョルジュ・プレートル指揮パリ音楽院管弦楽団(アルド・チッコリーニとアレクシス・ワイゼンベルグのピアノ)です。「ピアニスト」の所ではわざと2人の連弾をずらして弾くなど遊び心に満ちた演奏です。
交響曲第3番「オルガン付き」は録音の優秀なCDがいいですが、シャルル・デュトワ指揮モントリオール交響楽団で安心できるでしょう。ドイツ・オーストリア系のオケでもいいと思いますよ。
交響詩関係はフランス系のオケだったらまず間違いないでしょうが、ドイツ系でも結構名演はあるでしょう。お好みでどうぞ。
またいろいろご意見下さいね。